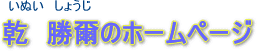 |
乾 勝爾のホームページ
| はじめに | 第四章 聖母マリア |
| 第一章 天地創造 | 第五章 十字架と復活 |
| 第二章 原罪 | 第六章 天国と地獄 |
| 第三章 イエス キリスト | 第七章 キリスト教と現代社会 |
|
カトリック教会は、日本では僅か45万人の信徒がいるだけであるが、世界では73億人の人口の内13億人の信徒がおり、その組織は、ローマ教皇の下に全世界に統一されている。宣教師ザビエルが1549年にキリスト教を日本に伝えた当時は、宣教師たちの熱心な伝道の結果、50年後の関が原の戦いの頃には我が国の人口1227万人の内、約40万人の信徒がいたといわれる。その後、徳川、秀吉の時代に禁制になったとはいえ、明治時代になって宗教の自由がいったん認められ、特に第二次大戦後、宗教の自由が憲法で保障されてからも、信徒はほとんど増えていない。
私の友人たちからよく聞くことは、キリスト教は、その教義が分かり難いといった声である。そこで私は、聖書から主な箇所を抜粋し、その教義についてもう一度考え直してみた。
私が洗礼を受けた昭和23年(1948年)頃は、キリスト教の教えを説いた公教要理といった小冊子がテキストであり、ドイツ人の神父から教わった。当時は旧約聖書は教えられず、新約聖書の一部分を教わり洗礼を授けられた。戦後間もない頃であったためキリスト教徒になる人も少なく、クリスマスになると豪華な飾りつけの中でミサが行なわれ、大きなデコレーションケーキを食べるパーティが開かれ楽しかった思い出がある。私の通っていた学校はミッションスクールの進学校であったため指導神父が、指導教官でもあり洗礼をすすめられて断ることは、よほどの事情がないかぎり不可能だったように思う。
(写真は、現存する日本最古のカトリック教会である長崎の大浦天主堂)
新約聖書には、イエスの生涯が描かれているが、中でもイエスの愛に満ちた行動は印象的である。著名なカトリック作家である遠藤周作は、著書「イエスの生涯」でイエスがヨルダン河でヨハネから洗礼を受けたあとガリラヤ湖畔での最初の活動を書いている。
ガリラヤの自然は美しいが、人間の生活はみじめで、この湖畔の村々には、隣人や家族からも見離された病人や不具者がいっぱいいた。司祭たちから蔑まれる収税人や娼婦のような男女もいた。聖書を読むと、イエスはほとんど偏愛にひとしい愛情でこれら人々から見棄てられた者、人々から軽蔑されている者のそばに近づいている。湖畔の村々にはマラリアの患者もおり、人々は彼らを悪霊につかれた者と忌み嫌ったが、その患者たちの看病もされている。町や村に近づくことを許されぬライ病人たちは律法によって神の罰を受けた者、不淨なものと見なされていたが、イエスはそのような律法さえ無視して、彼らを助けようとした。人々から馬鹿にされている収税人も弟子の一人に加えられ、人々が軽蔑する娼婦たちも決して拒絶されなかった。(レビ記13,14)
キリスト教は、愛の宗教といわれるが、新約聖書の中には、このような場面が、しばしば登場する。
「私があなたを愛したように、互いに愛し合いなさい。これが私の掟である」(ヨハネによる福音書15章12)と記載されている。イエスが掟として定めたのは、愛についてのこの箇所だけである。
またイエスは、律法の中でどの掟が重要かと尋ねられ、次のように答えている。「心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な掟である」第二も、これと同じように重要である。「隣人を自分のように愛しなさい」(マタイによる福音書22章37~39)
その愛の深さについては、新約聖書「コリントへの手紙1」の中で具体的に解説されている。「愛は忍耐強い。愛は情け深い。ねたまない。愛は自慢せず、高ぶらない。礼を失せず、自分の利益を求めず、いらだたず、憎しみを抱かない。不義を喜ばず、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える」(13章4~7)
キリスト教が愛の宗教と言われる所以である。
神なのか人なのか
 聖母マリアは多くのカトリック信徒の敬愛を受けている。聖母マリアは聖霊によって懐胎し神の子イエスを生んだ。(ルカ福音書1章26-38 マタイ福音書1章18ー25)
聖母マリアは多くのカトリック信徒の敬愛を受けている。聖母マリアは聖霊によって懐胎し神の子イエスを生んだ。(ルカ福音書1章26-38 マタイ福音書1章18ー25)
そのマリアについて聖書では、イエスの母であっても神ではなく、ただの女性として描かれている。イエス自身も最初の奇跡を行ったカナの婚礼の席で、マリアに「婦人よ」と呼びかけるなど母マリアを特別扱いにされていない。(ヨハネ福音書2章1-12)現在のカトリック教会の教えでも、マリアは三位一体の神とは区別され、神の母として崇敬の対象にはなるが、神ではないので崇拝の対象にしてはならないとしている。
しかしキリスト教の歴史を見てみると、地方によってはマリアは神格化された。教会も布教のために前文明期の母権社会で形成されていた地母神と一体化されることを黙認していた時代もあったようだ。
カトリック教会の教えの通り聖母マリアは神ではなく人なのだろう。しかしイエスが十字架に架けられたとき、十字架の側にいたのはイエスの母マリアに「婦人よ。ご覧なさい。あなたの子です」と言われ、弟子のヨハネに「見なさい。あなたの母です」と言われた(ヨハネ福音書19章25~27)。この言葉からすれば、やはり聖母マリアは、神ではなくてもイエスにとって母であり、弟子たちの母、信徒たちの母であり特別な存在であったと考えてよいように思われる。
写真はピエタの像、ミケランジェロ・ブオナローテイ 1498-1500年(サンピエトロ大聖堂)
イエスは、弟子ユダの裏切りによって捕らえられた(マタイ26章、マルコ14章、ルカ22章)。そのあとイエスは死刑の判決を受け、ゴルゴタの丘で十字架に架けられ苦しんで息を引き取った(マタイ27章、マルコ15章、ルカ23章、ヨハネ19章)
イエスが死刑の判決を受けたのは、ご自分が神の子だと宣言し、ユダヤ教を批判したためと言われているが、カトリックのカテキズムによると、ご自分の死によって最初の契約のもとで犯した人びとの罪すべてを贖うため生贄としてお捧げになった(ヘブライ人への手紙9章、詩編22章、イザヤ書53章、ダニエル書9章)と書かれている。
最初の契約のもとで犯した罪について聖書では次のように書いている。創世記の中でエデンの園に住まわされた男と女は神から「園のすべての木からとって食べなさい。ただし善悪の知識の木(知恵の木)からは決して食べてはならない」と言われていたが、女は蛇に誘惑されて神の命令に背き、女は知識の木の実をとって食べ、一緒にいた男にも渡したので男も食べた(創世記2章、3章)。この章では人間は、この時から神の命令に背き常に罪を犯すようになったと書かれている。イエスは、こうした人間のすべての罪を背負って十字架に架けられ神の許しを請われたというのがキリスト教の考え方のようだ。
イエスの復活は、イエスが磔刑に処せられ、死後3日目にマグダラのマリアらがイエスの墓に行ってみると、お墓が空になっており、そのあとイエスが女性信徒の前に現れ、その後もイエスは数回にわたって弟子たちの前に姿を表している。またイエスは、使徒トマスに「見ないで信じる者は幸いである」とも言われた。イエスが捕らえられた後、一度ならずイエスを裏切ったペトロなど弟子たちの前にも復活され、弟子たちも、この復活によって信仰を取り戻し、その後、全世界で宣教を行った。イエスは、復活後40日間地上に留まれた後、昇天された。(マタイ28章、マルコ16章、ルカ24章、ヨハネ20章、21章)
写真は「キリストの磔刑」マティアス・グリューネワルト 1512年-1515年 (ウンターリンデン美術館)
第六章 天国と地獄
天国と地獄と言えば、カトリックの総本山バチカン宮殿のシステイーナ礼拝堂にあるルネサンス期の芸術家ミケランジェロが描いた最後の審判の祭壇画を思い出す。中央では再臨したイエス・キリストが死者に裁きを下しており、左側には天国に上っていく人びと、右側には地獄に墜ちていく人びとが描写されている。
しかし聖書では天国と地獄について具体的に書かれた箇所は意外に少ない。唯一、新約聖書の最後におかれているヨハネの黙示録で天国と地獄について具体的に書かれている箇所がある。ヨハネの黙示録は紀元96年頃、小アジアのパトモス島でヨハネと言う人が幻視したことを書いたものと言われている。ただその内容が分かり難く、聖典として認められたのは2世紀になってからだという。
ここでは、終末を迎えた時すべての死者は復活する。海で死んだ者も、海が死人を波打ち際に打ち上げるので心配はない。その上、最後の審判を受ける。その結果、救われた人は豪華でピカピカな宝石に飾られた新しいエルサレムで神と一緒に楽しく永遠に暮らす。救われない人は硫黄が燃える池で焼かれ続ける。(ヨハネ黙示録19章~22章)
このヨハネの黙示録が書かれた当時は、全世界のキリスト教徒がローマ帝国によって迫害を受けていた。この書は、こうした人たちを励ますために書かれた書であるとも言われている。
キリスト教では、天国のことを神の国というが、イエスは神の国についてファリサイ派の人びとに神の国はいつ来るのかと尋ねられた時「神の国は見える形ではやって来ない。ここにある、あそこにあると言えるものでもない。実に神の国は、あなた方の間にあるのだ」と答えておられる(ルカ福音書17章20~21)。本当の天国は、イエスの教えを守り、人びとが愛と平和のある世界を作ることによって、何処においても実現できると考えるべきなのかも知れない。
写真は「最後の審判」 ミケランジェロ・ブオナローティ
1535年~1541年(システィーナ礼拝堂)
第七章 キリスト教と現代社会
神に最も近いイエスは、福音の中で「心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、あなたの神である主を愛しなさい」「隣人を自分のように愛しなさい」(マタイによる福音書22章27-39)と熱心に諭しておられる。イエスは、神の国を論ずるより神の国はこうした掟を守ることによって作ることが出来ると言っておられるようだ。
現代の混沌とした社会の中にあって、イエスの教えは一段と貴重なのではないか。私たちは、まずイエスに習い「愛のある世界、平和の世界」の実現を目指し努力することが大切なつとめだろう。それによって私たちの世界も神の国に少しでも近ずくことが出来るのではないか、と思われる。